坊っちゃん列車に乗ろう!
第28話「武士心」
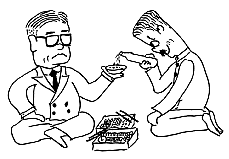 郡中線が電化された、本社の新築もなった。その祝賀会が新川の遊園地で盛大に二日間行なわれた。 郡中線が電化された、本社の新築もなった。その祝賀会が新川の遊園地で盛大に二日間行なわれた。社員一同は、折詰と清酒二合瓶、記念品をもらって、それぞれの職場毎に、祝宴を開いていた。 K君達、機関庫の連中も、松林の一角で輪になり適当に、祝宴を開いているが、職場が縮小されるので荒れ気味であった。 機関庫の連中に、酒を飲ますと、めんどいので、他の職場から敬遠されていた。前年の、道後公会堂での慰安会も、大荒れに荒れて、会場であばれ廻って、無茶苦茶にしてしまっている。 「Kよい、そこのからになった酒瓶に汐水汲んで来ておけ」 よしやとばかりK君、汐水を汲んできておいた。 「よし、今に見とれ、面白いことが始まるけんの」 チョボ監督さん、汐水で何かをたくらんでいるらしい。先程から、各職場の宴会の中を、廻っていた、度の強い目鏡をかけた太ったオッさんが、機関庫連中の輪のなかへ、どっかり座り込んで来た。 「社長、まずは一ぱい」 チョボ監督、大きな盃を社長に持たし、汲んできていた汐水を差し出した。K君達は、社長をこんな目の前で見るのは初めてであった。 一同は、まさかチョボ監督が社長に汐水を飲ますとは思っても見なかった。こいつは面白くなった。みんな注目した。 「おお、ここは機関庫の連中か、毎日ご苦労さんじゃのう、よし一ぱいもらおうか」 チョボ監督が、なみなみついだ汐水を一寸なめた社長、ぐっと一息に飲み干した。 「うまい」 一声発して、 「チョボ君、返盃だ」 チョボ監督が、持っていた汐水を取り上げ、逆に付出した。チョボさん、まさか自分が飲むつもりでなかったので目を白黒くしている。仕方なく、目をつむり、口をゆがめて一気に飲み干した。 「おお見事じゃ、もう一ぱいやれ」 「ええ・・・もうケッコウです」 「何を言うか、機関庫の代表人物、チョボ君がえんりょするな。わしの差し出す汐水、いやいや酒が飲めんと言うのか」 こいつは、ますます面白くなったと一同、息をのむ。 「ハア・・・イタダキマス」 社長も人が悪い。酔っている上に汐水を二杯飲まされたチョボさん。 「グエ・・・」 一声発して、のびてしもうた。 「さあ乾杯じゃ、まだ残っとるみんな飲め飲め」 社長は一同に、残っている汐水をついで廻った。K君達も汐水を飲まなければならない。自分が汲んで来た汐水あけん責任上勇気を出したK君。真先に、 「いただきまあす」 飲み干した。一同も我慢した飲み始めた。 「よしよし、見事じゃ。さずが機関庫の連中じゃ気に入った、そこの若いもん、わしじゃ言うて本部から、じゃん、じゃん酒をもって来い」 K君、言われて本部へ行き、社長の伝言を言うと、事務員さんが、じゃんじゃん、酒を運んできた。 「今日は、機関庫の連中と、とことんまでやるぞ」 社長は、上機嫌になって、太っ腹のとこを見せた。 「チョボ君、君等がわしに汐水を飲まし抵抗する気持はわかる、だが電化のために機関庫が縮小されることは辛棒してくれ、今度の事業は、近代化と共に社業発展のためにどうしても必要なことじゃ」 「社長、申しわけありません」 チョボ監督、感激し泣き出した、どうも泣き上戸のせいではなさそうである、こうなってくると貫禄の違いが出てしまった。 「よしよし、チョビヒゲを生した、大の男がそう泣くな、むかし戦国時代の武将が、敵に塩を送ってもろうたと言う有名な話があろうが、わしも、経営者として働く者から汐を送ってもろうた、お互いに戦国の武将になったような気持じゃのう」 社長、チョボ監督、そして機関庫の連中、一同意気統合して武士心、武士の心と語り合い、武士心とレッテルのある酒瓶を汲み交し、日の暮れるのを忘れてしまった。 やがて、連中の唄う機関庫の数え唄が、いつまでもいつまでも夕日の浜辺に続いていた。 機関庫の数え唄 一つとせ 人の皆知る機関庫の 若い健児の鼻の意気 ソイツァゴーキダネ 二つとせ 太い肝だよ、缶焚きは、脱線、転履なんのその ソイツァゴーキダネ 三つとせ 見れば見る程色黒い 線路の上では男前 ソイツァゴーキダネ 四つとせ 良くぞのぼった立花の 急な坂道なんのその ソイツァゴーキダネ 五つとせ いきな姿の缶焚きは ショベル片手で缶を焚く ソイツァゴーキダネ 六つとせ 無理に大学出なくとも 機関庫育ちで腕はたつ ソイツァゴーキダネ 七つとせ 長いレールを一走り 明日は郡中か横河原 ソイツァゴーキダネ 八つとせ やがておいらも出世して 末は機関庫助役様 ソイツァゴーキダネ 九つとせ 恋をするのはまだ早い 機関士になるまでその日まで ソイツァゴーキダネ 十うとせ 飛ばせ明治のマッチ箱 帽子のあごひも伊達じゃない ソイツァゴーキダネ (この唄は、誰が作ったか、何時頃から唄われていたかは知りませんが機関庫の連中が宴会などでは、良く唄われており、何時の間にか、若い者達に受け継がれていました。) |
| 附記 昭和二十五年、郡中線が電化となり、本社、市駅、マーケットが新築されました。 郡中線の電化は、会社全体として喜びであり、将来に向っての発展であった出来事ですが、私達、機関庫の者にとっては、隅に追いやられたような淋しさがありました。 電化と共に、人員減少で、十数名が電車の運転士、車掌として勤務となり、その後、バスの車掌、整備員として順次転勤がありました。 私も、昭和二十八年五月、バス車掌として転勤をしました。 郡中線電化後は、高浜線との間に挟まれた低いホームから、森松、横河原方面へ出発する列車は、黒煙を吐き、客車も昔型で近代化された電車と比較して、肩身のせまい思いで運転しておりました。 今、考えますと、横河原線も電化となり良かったと思いますが、森松線が廃線となったのは惜しいような気がしてなりません。 この物語の社長さんは、梅津寺駅から電車で通勤されていましたが、空席があっても、絶対、座席に座らず、つり皮に手をやり立っておられました。 座席は、お金を出して乗っていただいているお客さんのものであり、ただで乗っている社員が座席に座ることは、お客に申しわけないと、自らが手本を示された姿でした。 私も、その姿に接したことがありましたが、鉄道員として頭の下る思いがしました。 当時の社員も、伊予鉄の社員としての気質があり、制服、制帽受給者は、きちっと、制服着用で通勤しておりました。その服装ですから、電車や、列車で空席があっても座る事は出来ませんでした。 機関庫員と、電車、客車の検車係員は、制服に制帽、それに仕業服支給されていましたので、他の職場と比較して得をしているような気持でありました。 私は、退社するまでの四十四年間制服を受給される職場でしたので、着るものには大助りでした。退社して私物ばかり着ていると何か、しゃっきとしない感じがします。 “汽笛一声 電車に負けぬ 意地があり” |